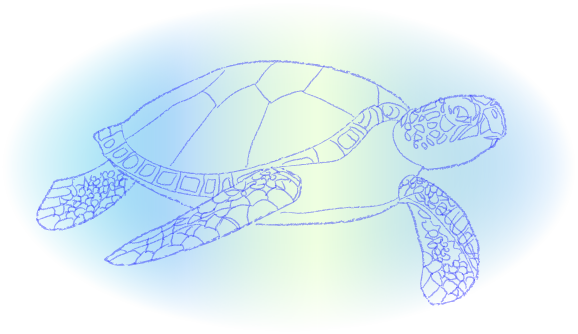塩炊き小屋
「静間ふるさと交流倶楽部」手書きの看板が出迎えてくれます。昔は、それぞれの地域で、塩を作っていたそうです。

小屋の周り
塩焚き釜に使う木材は、古い家屋の柱や電柱など、廃材を使っています。暮らしの中で、最後まで物を大切に、有効活用する。昔の人はずっとそうしてきました。

小屋の中の様子
多くの塩を焚くためではなく、子供達に体験してもらうのに、丁度よい広さを保つためにと、塩焚きの釜は2基。 効率よく作業できるように考えられています。 右と左の釜はそれぞれ役目が違うそうです。よく見ると左右の釜の高さが違うのです。
整理された道具達
以前は多くの子供達が、ここで塩焚きの体験をされたそうです。体験用の小さな鍋が子供たちの笑顔に見えてきます。


海からの恵み
海藻を集め、煮詰めて藻汁にし、塩に混ぜます。見せていただいた海藻の表面には塩がついています。古代の人はこれを見つけて塩づくりを始めたのでしょう。