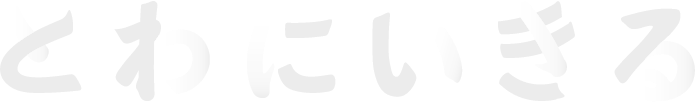独楽庵 復元
About
茶庭をぐるっと一周
独楽庵とは、茶の湯の大成者・千利久が豊臣秀吉から名橋・長柄の橋杭をもらい、建てられた歴史ある茶室です。
千利休のお茶室がなぜ島根の文化施設で復元されているのか?不思議に思われたかもしれませんが、このお茶室は様々な人の手に渡ったあと、最後に松江藩主であり大名茶人であった不昧公が所有していたのです。

不昧公とは?
松江藩七代藩主・松平治郷。人々から「不昧公」と呼ばれ親しまれていますが、「不昧」とは晩年、号(ペンネームみたいなもの)として名乗った名前です。松江藩の財政難を立て直したという功績の一方で、十代の頃から茶の湯や禅学を学ぶ文化人でもありました。




Recommendation
独楽庵(復元)おすすめポイント
千利休と不昧公が
好んだ名席

千利休が生み出し
不昧公が守り継いだ名席
大名茶人として有名な不昧公は、江戸・大崎に2万坪もの屋敷地を持ち、そこにはいくつもの茶室を作りましたが、その中でも中心になっていたのは茶の湯の大成者・千利久好みの独楽庵でした。
独楽庵は災害により失われてしまいましたが、出雲文化伝承館に再現された独楽庵は、茶室だけでなく茶室までの露路や意匠も復元されています。
独楽庵(復元)の周りの露地・茶庭を散策できます。 たまにカエルが跳ねています。

取材当時、独楽庵の一部が修繕中でした。このHPが公開される頃には工事が終わっているはずです。ぜひ遊びに行ってブルーシートのない露地を歩いてみてください!

泥壁に自然と
生まれるサビ

泥壁に自然と生まれる
サビは楽しむもの
泥かべに自然と生まれる黒いサビを、当時は景色として楽しんでいました。現代の感覚からすると「サビ!?」と驚かれるかもしれませんが、自然に生まれた変化を慈しむ気持ちは、お茶に親しむ時代に生まれた心です。

かわいい形の作。

特別に中潜を潜らせていただけました。
禅の精神と
おもてなしの心

藩主が自らもてなす
おもてなしの心
利久席は2畳という限られたスペースです。そこでは不昧公自身が、お茶や懐石料理を手渡します。不昧公が学んだ禅の精神は、今日のおもてなしにも繋がるお茶の根底の心です。


夏の日差しに照らされた露地。

ものすごく細かい萱葺(かやぶき)屋根。
独楽庵(復元)
まとめ

利休席は2畳ですが、この小間のお茶室で4時間茶事が行われていたそうです。お抹茶だけいただくわけではなく、食事が出されたり、間にお庭を見ながら休憩を挟んでの4時間です。
出入りする間に、掛け軸を片付けてお花を生けるなど、おもてなしは多岐に渡ります。茶会の呈主も大変だと思いますが、招客として招かれる側はとても楽しいイベントだろうと思いました。