島根県西部に位置する、大田市から浜田市に至る地域に発達した窯業は、一般的に「石見焼」と呼ばれています。 その中でも最近は、温泉津町の窯業は「温泉津焼」と呼ばれており、石見地方の焼物文化の一つでもあります。

温泉津焼の歴史
温泉津焼は、宝永年間(1704-1708) に三窯が開かれたことから始まります。その後、江戸末期、江津地区の職人により温泉津焼の技術改良が 行なわれ、幕末から明治中期(1830-1890)にかけて多く開かれたと伝 えられます。
江戸時代から明治時代にかけては、北前船(日本海沿岸の各港に寄って、各地で特産品を売買する船)が温泉津港に寄港し、石見銀山の銀などと共に、温泉津焼(はんどなど)が全国に積み出されていました。当時の温泉津は、実用容器の産地として栄えた地域でもありました。

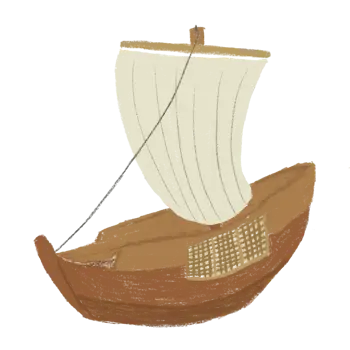
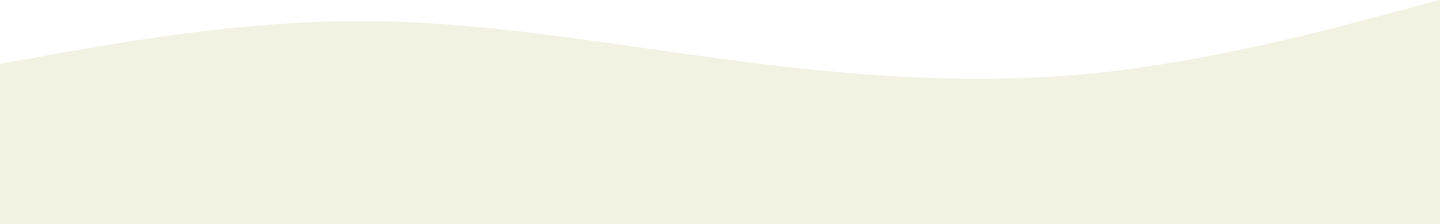

はんど(Hando)
水を貯蔵するための水瓶のことで、 半斗、飯胴、半銅(はんどう)とも呼ばれる
水を貯めておくために利用されたり、漬物をつけたり、味噌の醸造にも用いられています。とくに石見焼・温泉津焼の良質な陶土で作られる茶褐色のはんどは、丈夫で耐水性や耐酸性に優れているため、「石見の丸物」として多くの人に親しまれました。

歴史はこうして繋がれた
実は温泉津焼がなくなりかけた?!
大正時代に入ると、鉄道の開通や温泉津港の商業港としての機能が薄れたことに加えてプラスティック製品の普及によって陶器の需要が一気に落ち込み、衰退に追い込まれた温泉津焼。
その時ピンチを救ったのは ...!
1969(昭和44)年当時、河井寛次郎氏に師事していた荒尾常蔵氏が温泉津に移住したことによって、温泉津の焼物の衰退を免れました。その時に、登り窯も改築されました。

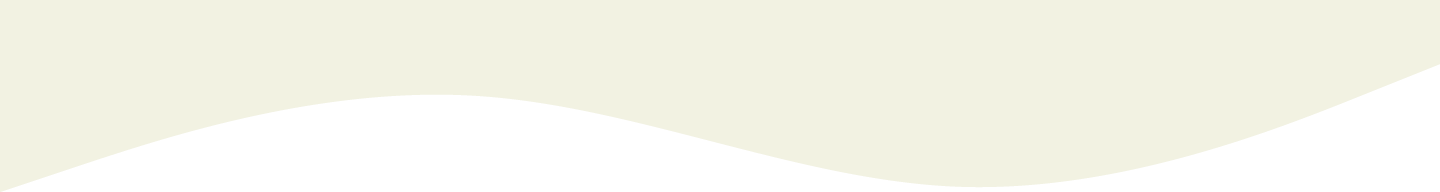

登窯( Noborigama)
登り窯の特徴として、複数の窯が階段状に連なった形をしているのがポイントです


各窯には横口と呼ばれる薪を投げ入れる小窓があり、上段の窯とは底部の格子状の窓でつながっています。下の段で焚いた温度が次の窯へ伝わり、効率よく焼成ができる仕組みになっています。

国内でも最大級を誇る2つの登窯

笹屋窯
温泉津には、国内でも最大級レベルの大きさを誇る登窯が2基あります。
やきもの館のすぐ横にあるのは笹屋窯で、なんと15段の全長30mの大きな登窯です。下から見上げてみると、その存在感に圧倒されます。

横手窯
笹屋窯のさらに左手にあるのが横手窯で、笹屋窯より5段分少ない、10段の全長20mの登窯です。

登窯の一番下(1段目)の大口と呼ばれる窯は、陶器を入れない仕様となっています。大口の窯には、薪を入れて火を付け、温度を上げるための役割があり、その温度は最高1300度までに到達されると言われています。



